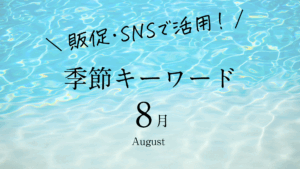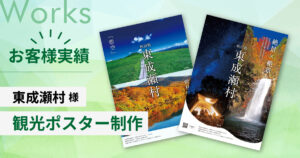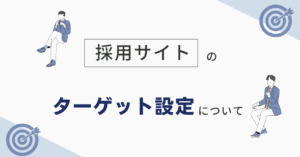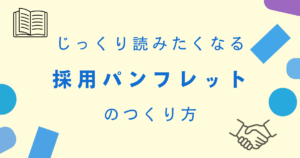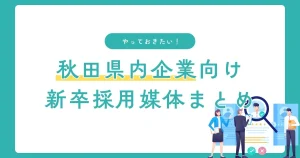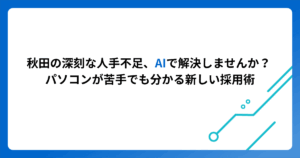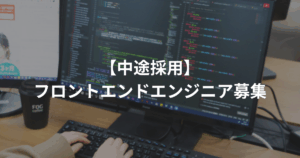企業の成長を支える人事・採用担当者、そして経営者の皆さま。
「その採用広告、本当に『欲しい人材』に届いてますか?」
8月に入り、新卒採用であれば2027年卒に向けて、キャリア採用であれば通年を通して、既に採用活動をなさっている最中かと思いますが、同時に多くの方々がこんな課題に直面しています。
「高いお金を払っているのに、欲しい人材からの応募がさっぱり来ない…」
「せっかく採用したのに、すぐに辞めてしまった…」
「また採用広告費が予算を圧迫している…」
なぜなら、かつては当たり前だった「広告を出して応募を待つ」という採用スタイルは、今や限界を迎えつつあります。求職者はきれいに整えられた広告よりも、その企業の「リアルな姿」を知りたがっているからです。
もし、高額な広告費をかけず、自社の魅力で未来の仲間を引き寄せられるとしたら…?
その答えが、今回ご紹介する「コンテンツ採用」です。
この記事では広告費に頼らず、会社の本当の魅力で未来の仲間を引き寄せる、新しい採用の「仕組み」をお伝えします。
「なんだか難しそう…」「うちみたいな中小企業には無理だよ」と感じた方も安心してください。
今回は人事担当者がたとえ1人でも、今日から始められる「コンテンツ採用」の優しい教科書です。
読み終える頃には広告費にサヨナラし、自信を持って情報発信を始める第一歩を踏み出せるはずです。
なぜ今、「コンテンツ採用」なのか?広告頼りの採用が限界な3つの理由
そもそも、なぜ従来型の採用広告だけではうまくいかなくなってしまったのでしょうか。その背景には、求職者の行動や価値観の大きな変化があります。
理由1:求職者は「リアルな情報」を求めている
考えてみてください。仮に就職先・転職先を探すとき、キラキラした広告のキャッチコピーだけを信じますか?
おそらく、企業の口コミサイトを見たり、SNSで社員の投稿を探したり、実際に働いている人の「生の声」を探したくなりますよね。
現代の求職者は、企業が発信する「公式」の情報と同じくらい、あるいはそれ以上に、働く人の日常や企業のカルチャーといった「非公式」でリアルな情報を重視しています。広告だけでは、その企業の本当の姿は見えてきません。
理由2:上がり続ける採用コストと、見えない費用対効果
採用広告費は、年々高騰する傾向にあります。多くの企業が同じパイを取り合うため、どうしても価格競争になってしまうからです。
多額の費用をかけても、応募が来るかは「運次第」。これでは、まるで終わりの見えないギャンブルですよね。限られた予算の中で、より確実性の高い方法に投資したいと考えてしまうのも当然です。
理由3:採用のミスマッチが引き起こす、静かな経営ダメージ
「待遇は良いはずなのに、なぜか人が定着しない…」
「ようやく一人前に育ったと思ったら、退職届が…」
こんな経験に、胸が痛む方も多いのではないでしょうか。
これは、スキルや経験といった表面的な条件は合っていても、企業の価値観や文化(カルチャー)といった、もっと根っこの部分で「採用のミスマッチ」が起きているサインかもしれません。
①.目に見える「直接的なコスト」の損失
まず分かりやすいのが、金銭的な損失です。一人の社員が早期離職した場合、これだけのコストが無駄になってしまいます。
- 採用コスト: 数十万~数百万円にのぼる広告掲載費や人材紹介手数料。
- 人件費・教育コスト: 入社手続き、社会保険料、研修費用、そしてOJT(実務研修)で指導にあたった先輩社員の時間(給与)
これら全てが水の泡となります。一般的に、一人の早期離職者が出す損失は、その社員の年収の半分から2倍に相当するとも言われています。これは、利益を圧迫する非常に大きなインパクトです。
②.より深刻な、目に見えない「間接的なダメージ」
しかし、本当に怖いのは、金銭的損失よりもこちらの「目に見えないダメージ」です。
- 生産性の低下と現場の疲弊: 退職者が出れば、その穴を埋めるために他の社員の業務負荷が増大します。引き継ぎや欠員補充のための採用活動で、現場はどんどん疲弊。「本来やるべきだった仕事」が進まなくなり、組織全体の生産性が著しく低下します。
- 職場の士気(モチベーション)低下: 「また人が辞めた」「うちの会社には何か問題があるのでは…」というネガティブな空気は、伝染病のように職場全体に広がります。真面目に頑張っている社員のモチベーションまで削いでしまいます。
- 「連鎖退職」のリスク: 特に、チームの中心人物やムードメーカーがミスマッチを理由に辞めてしまうと、「〇〇さんが辞めるなら自分も…」と、優秀な人材が流出する「負の連鎖」を引き起こす危険性もはらんでいます。
- 社外的な評判(レピュテーション)の悪化: 退職者が増えれば、「あの会社は人がすぐ辞める」という評判が、転職口コミサイトやSNSを通じてあっという間に広がります。一度ついたネガティブなイメージを払拭するのは非常に困難で、将来の採用活動をさらに厳しいものにしてしまいます。
このように、採用のミスマッチは、単に「一人が辞めた」という話では済みません。組織の内部からじわじわと蝕み、成長の芽を摘んでしまう。静かですが、極めて深刻な経営課題となります。
「コンテンツ採用」とは?企業の魅力を”資産”に変える新しい採用のカタチ
ミスマッチを継続的に少なくしていくには?
一言でいえば、「資産をつくる」です。
つまり、「自社でコンテンツ(情報)を作り発信することで、企業のファンを増やし、自社の魅力に共感してくれる人材からの応募を募る採用手法」のことです。
企業ブログや社員インタビュー、SNSでの発信などを通じ自社の「ありのままの姿」を継続的に伝えることで、求職者との間に信頼関係を築いていきます。
例えるなら、広告は「短期決戦のチラシ配り」、コンテンツ採用は「ファンを作るための雑誌作り」のようなもの。一度作ったコンテンツは、インターネット上に残り続け会社の魅力を伝え続けてくれる「資産」になります。
コンテンツ採用の3つの大きなメリット
- 採用コストを大幅に削減できる:自社で情報を発信するため、高額な広告費は必要ありません。noteやSNSなど、無料で始められるプラットフォームもたくさんあります。
- 採用のミスマッチを劇的に減らせる:仕事内容だけでなく、社風や働く人の人柄といったリアルな情報を事前に伝えることで、求職者は「自分に合う会社か」を判断しやすくなります。結果として、カルチャーフィットした人材からの応募が増え、入社後の定着率も向上します。
- 企業のブランディングにも繋がる:継続的な情報発信は、「この会社は、働く人を大切にしているんだな」「面白そうな取り組みをしているな」というポジティブなイメージを社外に広げ、採用だけでなく、事業そのものにも良い影響を与えます。
人事ひとりでもOK!コンテンツ採用を始めるための簡単3ステップ
「メリットはわかったけど、何から始めれば…?」
ご安心ください。ここからは、誰でも始められる具体的な3つのステップをご紹介します。
ステップ1:誰に、何を伝えるか?「ペルソナ」と「自社の魅力」を再発見しよう
まず、闇雲に発信するのではなく、「誰に」「何を」伝えたいのかを明確にしましょう。
① 理想の仲間像(ペルソナ)を具体的に描く
「〇〇部のAさんのような、周りを巻き込む力がある人が欲しいな」といったように、実在の社員をモデルに考えてみると、イメージが湧きやすくなりますよ。
② 自社の「当たり前」に隠された魅力を見つける
- 働きがい: どんな時にお客様から「ありがとう」と言われる? プロジェクトが成功した時の達成感は?
- 文化・風土: 社員同士のコミュニケーションは活発? ちょっとユニークな社内制度やイベントはない?
- 人: 目標に向かって頑張っている社員は? 新しいことに挑戦している社員は?
ぜひ、同僚や上司にも「うちの会社の良いところって何だと思う?」と聞いてみてください。自分では気づかなかった魅力的なポイントが、きっと見つかるはずです。
ステップ2:何で伝えるか?「コンテンツの種類」と「発信メディア」を選ぼう
次に、見つけた魅力をどんな形で、どこで発信するかを決めます。
①代表的なコンテンツの例
- 採用ブログ: 社員の1日の仕事の流れ、プロジェクトの裏話、社内イベントのレポートなど、会社の日常を伝えるのに最適です。
- 社員インタビュー: なぜこの会社に入社したのか、仕事のやりがいは何か、などを語ってもらうことで、求職者は働くイメージを具体的に持つことができます。
- 会社紹介資料(採用ピッチ資料): 事業内容やビジョン、働く環境などをまとめた資料。Wantedlyなどに掲載すれば、会社の全体像を深く理解してもらえます。
②おすすめの発信メディア
- 自社サイト内のブログ: SEO対策を意識すれば、検索エンジンからの流入(アクセス)が期待できます。
- note: デザインがおしゃれで、文章を書くことに集中できるプラットフォーム。ハッシュタグを使えば、多くの人に見てもらえるチャンスがあります。
- Wantedly: 「共感」で会社と人をつなぐビジネスSNS。ブログ機能(ストーリー)があり、企業のファンを作りやすいのが特徴です。
ポイントは、最初から全部やろうとしないこと。まずは一番始めやすいブログから、1つのメディアで発信してみるのがおすすめです。
ステップ3:どうやって続けるか?「無理なく発信」を習慣化するコツ
コンテンツ採用で最も大切なこと。それは「続けること」です。
① ネタは探すものではなく、拾うもの
日々の業務の中に、コンテンツの種は転がっています。「新入社員が初めて契約を取った」「エンジニアチームが新しいツールを導入した」など、社内の小さなニュースをメモしておきましょう。
② 完璧を目指さない。60点でGO!
「完璧な文章を書かなければ…」と気負う必要はありません。大切なのは、熱意とリアルさです。まずは60点の出来でもいいので、世に出してみる勇気を持ちましょう。
③ チームを巻き込む
「来週、30分だけ話聞かせて!」と同僚にインタビューを依頼したり、「ブログに載せるから、プロジェクトの写真撮っておいて!」とお願いしたり。周りを巻き込むことで、ネタも集まりやすくなり、あなた一人の負担も軽くなります。
これだけは押さえたい!求職者に読まれるコンテンツ作りの3つの秘訣
最後に、あなたの発信を「読まれるコンテンツ」にするための秘訣を3つ、お伝えします。
秘訣1:「自分ごと化」させるストーリー
人は、単なる情報の羅列よりも、物語(ストーリー)に心を動かされます。「こんな困難があったけど、チームでこう乗り越えた」といったストーリーは、読者に「自分もこの仲間と働いてみたい」と感じさせる力があります。
秘訣2:企業の「素顔」を見せる正直さ
良いことばかりを並べるのではなく、時には課題や失敗談も正直に話すことが、かえって信頼に繋がります。また、「私たちはまだ発展途上ですが、こんな未来を目指しています」という姿勢は、誠実な人柄として求職者に伝わりやすくもなります。
秘訣3:届けるための、ちょっとしたSEOのコツ
- キーワードを意識する: 求職者がどんな言葉で検索するかを想像し、その言葉(例:「中小企業 採用」「エンジニア 働きがい」など)を記事のタイトルや見出しに入れてみましょう。
- タイトルは具体的に: 「採用ブログ始めました」ではなく、「【社員インタビュー】元営業職の私が、未経験からマーケターに挑戦した理由」のように、誰が・何を・どうしたのかが分かるタイトルにすると、クリックされやすくなります。
まとめ:小さな一歩が、未来の仲間と出会う最短の近道
コンテンツ採用は、種をまき、水をやり、太陽の光を浴びさせて、ゆっくりと育てていく農作業に似ています。すぐに大きな実りは得られない場合が多いです。
しかし、丁寧に育てた土壌からは、健康的で美味しい作物が育つように、継続的な情報発信は、企業の文化に深く根ざし、広告費では決して買うことのできない「共感」という名の応募を、安定してもたらしてくれるようになります。
それは、会社にとってはもちろん、人事担当者にとってもかけがえのない「資産」になるはずです。
1日でも早く始めてみましょう。
その魅力、私たちが届けます。
この記事を最後まで読んでくださったあなたは、きっと現状をどうにか変えたいと考えていらっしゃると思います。
「すぐ取り掛かった方が良いのは分かってる。でも、何から手をつければいいのか…」
その一歩を踏み出すお手伝いをさせてください。なぜなら、私たちが提供するのはモノではなく「仕組み」だからです。
例えば、Webサイトなら「訪問者をどうコンバージョンへ導くか」、SNSなら「どんな投稿でエンゲージメントを高めるか」、チラシなら「最適なデザインは何か」を深く掘り下げ、成果につなげられるよう機能する仕組みを考えることができます。
そして、貴社の当たり前に隠された「魅力」や働く人の「想い」を丁寧にヒアリングし、未来の仲間の心に響くコンテンツをカタチ創ることを得意としています。
まずは「こんな会社にしたい」という、想いをお聞かせください。