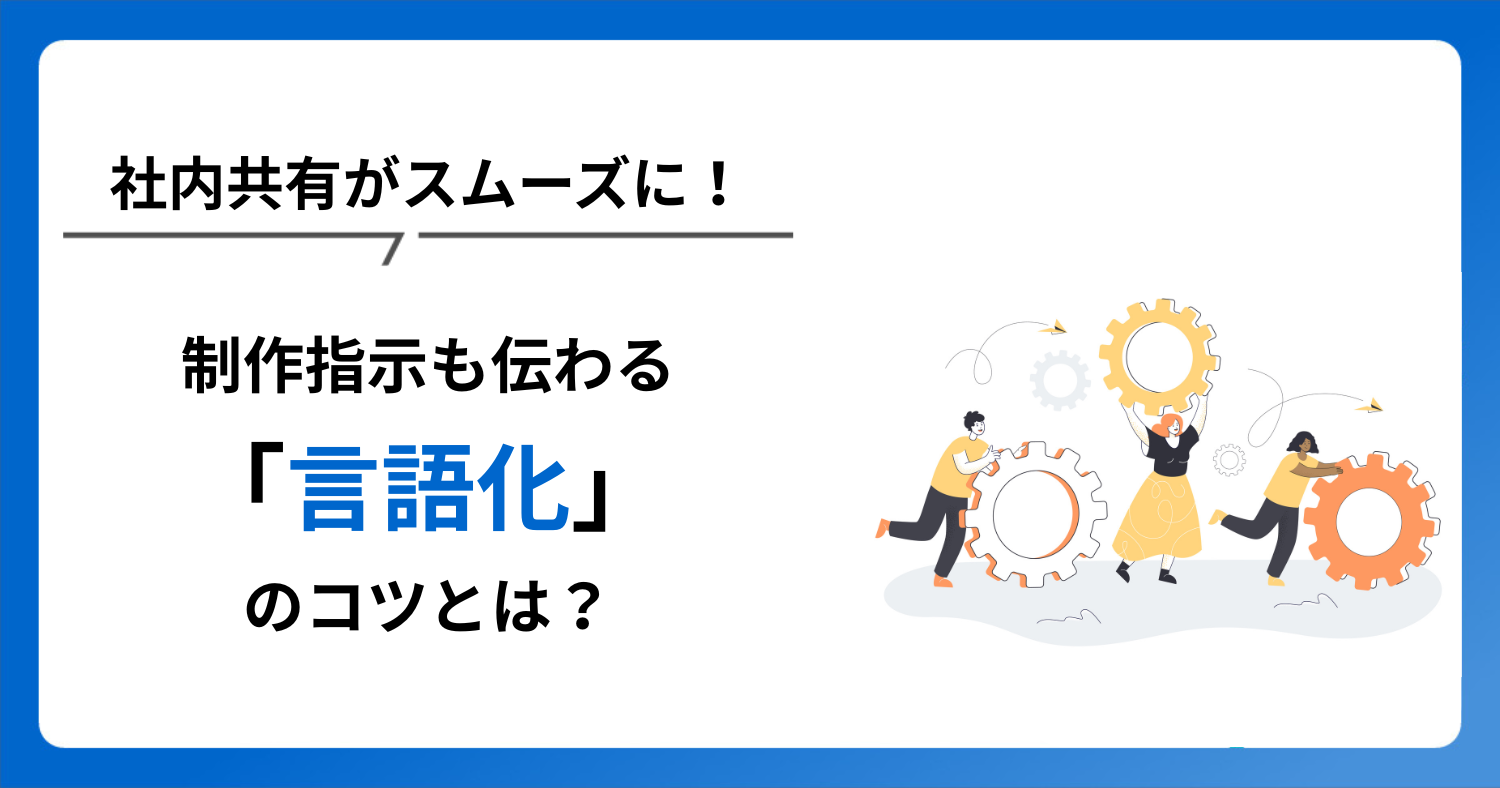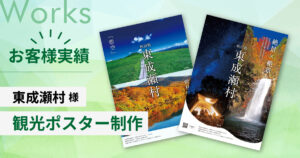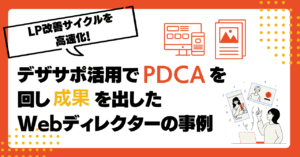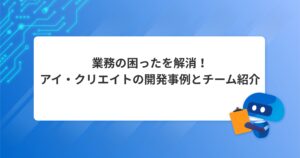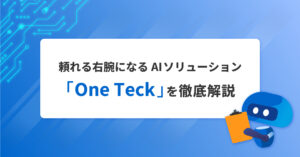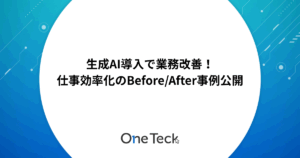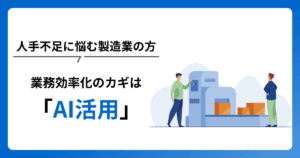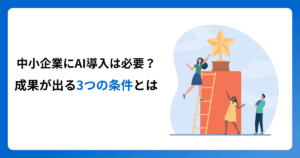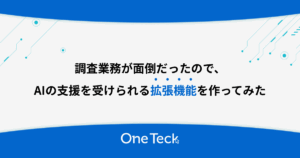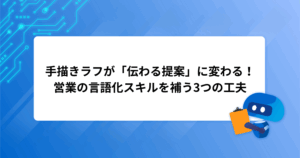制作チームに依頼を出したはずなのに、意図がうまく伝わらず、修正やすれ違いが発生。
「もっとちゃんと伝えたかったのに…」と感じた経験はありませんか?
営業やディレクターなど、言葉で伝える機会が多いビジネスパーソンにとって、
社内共有や制作指示での「言語化力」は業務効率に直結する重要なスキルです。
しかし、毎回丁寧に文章を組み立てるのは手間がかかるし、忙しい現場では現実的ではありません。
そこで今回は、制作指示が伝わる言語化のコツと、日々の業務で実践できる工夫をご紹介します。
さらに、すべてを自分で言語化しきれないときに役立つサポートツールもあわせてご紹介します。
ではまず、なぜ社内で「伝わらない」問題が起きやすいのかを見ていきましょう。
社内共有で起こる「伝わらない」問題とは?

制作指示の言葉があいまいで起こる誤解
制作チームにラフ案や口頭の説明を渡したものの、完成物を見て「思っていたものと違う…」と感じたことはありませんか?
その原因の多くは、言葉の選び方や情報の粒度の違いによる解釈のズレです。
たとえば、「もっとインパクトのある感じで」といった抽象的な表現では、受け手が何をもってインパクトと捉えるかは人それぞれ。
その結果、期待と成果物の間にギャップが生まれてしまうのです。
属人化による情報共有の非効率さ
営業個人の感覚や経験に頼った指示は、属人化しやすく、再現性が低いのが課題です。
社内メンバーが代わりに対応する場合や、制作担当が変更になったとき、共有内容の不足や曖昧さが原因で進行に時間がかかることも。
属人化を防ぐためには、誰が見ても理解できるよう情報を構造化して伝える力が求められます。
営業が感じる言語化の負担とストレス
「言いたいことは頭にあるけど、文章にするのが難しい」
「伝えるために毎回文章を組み立てるのが面倒」
そんな言語化ストレスを感じている営業担当者は少なくありません。
特に、資料作成や商談準備で多忙な中、
社内向けの制作指示や情報共有にまで手が回らず、「伝える努力」が後回しになってしまうこともあります。
しかし、ここで伝え方を誤ると、後々の修正対応や手戻りが発生し、結果的に工数が増えることに。
この悪循環を断ち切るには、無理なく続けられる「言語化のコツ」を押さえておくことが重要です。
伝わる制作指示のための言語化3つのポイント
営業が制作チームと円滑にやりとりするには、「ラフがあるから伝わるだろう」では不十分です。
ポイントを押さえて言語化することで、認識のズレを最小限に抑えることができます。
ここでは、誰でもすぐに実践できる3つの言語化テクニックをご紹介します。
①目的や狙いをシンプルに伝える
まず大切なのは、「この提案・制作物で何を実現したいのか」という目的や狙いを端的に伝えることです。
例:
✕「かっこいい感じで」
〇「新規の若年層向けに、親しみやすくも勢いを感じるデザインにしたい」
制作側が方向性を正しく理解するためにも、「なぜこの見せ方なのか?」という背景情報は非常に重要です。
② 具体的な理由や背景を添える
「この色を選んだ理由」「この配置にしたい意図」など、判断の裏にある理由をひと言添えることで、
制作者側の納得度が高まり、意図を汲んだアウトプットが返ってきやすくなります。
例:
✕「もう少し強調してください」
〇「この部分が競合優位性のため、強調したいです」
言葉に意味づけがあるだけで、やりとりの精度が大きく変わります。
③ 専門用語や曖昧な表現を避ける
「雰囲気よく」「ちょっと派手めに」などの曖昧な表現は、誤解のもとです。
また、業界内の略語や専門用語も、全員が同じ理解をしているとは限りません。
なるべく、共通言語で具体的に説明することを意識しましょう。
例:
✕「インパクトのあるビジュアルで」
〇「メイン画像を大きく配置して、視線を引く構成にしたい」
相手が制作のプロであっても、伝え手の意図を翻訳可能な言葉で伝えることが成功の鍵です。
忙しい営業でも実践できる言語化の工夫

「言語化が大事」と分かっていても、営業は日々の業務に追われてなかなか時間が取れないのが実情です。
このセクションでは、忙しい営業でも無理なく取り入れられる言語化の工夫をご紹介します。
メモやラフを活用して言葉を整理する方法
頭の中にあるイメージを、いきなり文章にするのはハードルが高く感じるもの。
そこでおすすめなのが、手書きのラフや箇条書きメモを活用する方法です。
まずは以下のような項目をざっくり書き出すだけでも、
頭の中の情報が整理され、言語化の土台ができます。
- 誰に伝えたいのか(ターゲット)
- 何を強調したいのか(主メッセージ)
- なぜそうしたいのか(背景や目的)
こうした情報を可視化することで、自分の意図もクリアになり、指示の精度も向上します。
共有ツールやテンプレートの活用術
ゼロから毎回文章を組み立てるのは負担が大きいため、
共有ツールとテンプレートの活用も非常に効果的です。
たとえば、以下のような簡易テンプレートをあらかじめ用意しておくと、
誰でもスムーズに制作指示が出せるようになります。
制作指示テンプレート例:
- 案件概要:〇〇〇〇
- ターゲット:〇〇〇〇
- 表現の意図・方向性:〇〇〇〇
- 参考資料や参考URL:〇〇〇〇
Google DocsやNotionなどのクラウドツールを使えば、複数人での編集や履歴管理も簡単に行えます。
チームで使える「言語化の型」を作る
属人化を防ぐために有効なのが、チーム共通で使える言語化の型を整備することです。
営業チーム内で「このフォーマットに沿って書くと伝わりやすい」といった成功パターンを蓄積し、共有することで、
誰が担当しても一定のクオリティで制作チームと連携できるようになります。
さらに、制作側からのフィードバックも反映して、
「こう書くと伝わりやすい」「ここは必ず書いてほしい」といった相互理解のルール化が進めば、
指示のやりとりにかかる時間や労力を大きく削減できます。
言語化をサポートする便利なツール紹介

「頭では分かっているけど、やっぱり言葉にするのは難しい」
そんな時に頼れるのが、言語化をサポートしてくれるツールの存在です。
ツールを上手に活用することで、営業担当の負担を減らしつつ、
より正確に、よりスピーディに社内共有や制作指示を行うことができます。
文章作成の負担を減らす自動生成ツールとは?
最近では、ラフやメモ、要点だけを入力すれば、自動で文章を構成してくれるツールが増えています。
たとえば以下のような課題に対応できます。
- 断片的な情報しかないが、整った説明文にしたい
- 指示書や共有用の資料を作る時間がない
- 自分の表現に自信がないが、ニュアンスを正確に伝えたい
これらのツールは、テンプレートや文脈補完の仕組みを活用し、営業の「伝えたいけど書けない」を解消する強い味方になります。
One Teck Writerがもたらす具体的な効果
中でもOne Teck Writerは、営業と制作をつなぐ「言語の橋渡し」として設計されたツールです。
営業の頭の中にあるアイデアやラフスケッチをもとに、「伝わる文章」へと変換する機能を持っています。
主な特徴は以下の通りです。
- 手書きラフや箇条書きをもとに、制作向けの指示文へ整形
- 提案資料や説明文の言語化の型があらかじめ用意されている
- 営業が使いやすいUI/直感的な入力設計
結果として、制作への指示が正確になり、手戻りが減少/社内コミュニケーションが円滑化します。
さらに、属人化しやすい「伝え方」を標準化できるため、チーム全体の業務効率も向上します。
導入のポイントと活用シーン
One Teck Writerは以下のような場面で特に効果を発揮します。
- 制作指示や企画共有が曖昧で伝わりにくいと感じるとき
- 営業資料・提案書の「文章部分」にいつも時間がかかるとき
- 社内メンバーとの意思疎通にすれ違いを感じているとき
導入時のポイントは、まずは一部チームで試験運用し、実際の業務にどうフィットするかを見極めること。
そのうえで、自社の共有フローに組み込むことで、スムーズな展開が可能になります。
まとめ
営業が社内で制作チームとやりとりする中で、「伝えたつもりが伝わらない」という壁はつきものです。
しかし、ちょっとした言語化の工夫を取り入れることで、提案の説得力や社内の連携は大きく変わります。
本記事でご紹介したポイントをおさらいすると
- 目的や意図を明確に伝えるだけで、指示の精度が上がる
- メモやラフをベースにした言語化で、手間を最小限に
- テンプレートや型の活用で、チーム全体の質を底上げできる
とはいえ、毎回これを完璧に実行するのは難しいのも事実。
だからこそ、One Teck Writerのようなツールの力を借りることで、
忙しい営業の日常業務に“伝わる言葉”を自然に組み込むことができます。
「なんとなく」で伝える時代から、「ちゃんと伝える」チームへ。
その第一歩として、ぜひOne Teck Writerを活用してみてはいかがでしょうか。
ご相談・お問い合わせ
One Teckでは、現場課題に応じたAI活用のご提案や、無料トライアルのご案内も行っています。
まずはお気軽に、資料ダウンロードやご相談から。