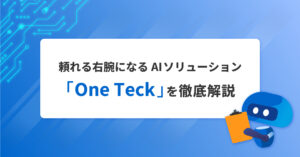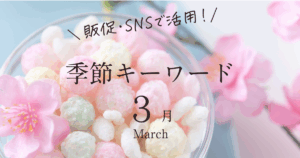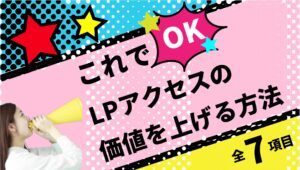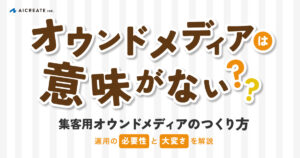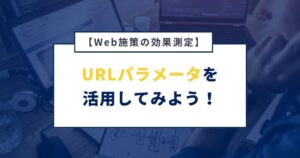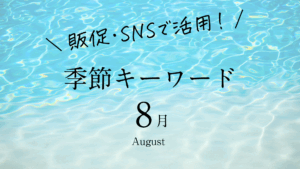「またあのお店に行きたい」
「あの商品をもう一度買いたい」
店舗やサービスの運営を担っている皆さんは、顧客にそう思ってもらえるような関係構築を目指していませんか?
今回は顧客の心を掴み、リピート購入へと導く強力な方法をいくつかご紹介します。
リピート購入の深層心理:なぜ顧客は繰り返すのか?

経験財から探索財へ:購買前の情報収集の変化
消費者の購買行動の変化は、企業にとって新たなチャレンジである一方で、新しいチャンスでもあります。
なぜなら、今の消費者は購入に先立ち多くの情報をネットから収集し、商品の詳細やレビューを比較しているからです。その結果、以前は実際に購入しなければわからなかった商品の質や使い勝手が、今では購入前に理解できるようになりました。
また、SNSによって消費者は個々の購買体験を共有し、他の消費者の意思決定に大きな影響を与えるようになっています。
商品の比較が容易になったことで、消費者は価格だけでなく、「品質や機能性、ブランドイメージといった様々な要素を考慮して選ぶ」という動きが一般的となり、商品の価値を明確に伝え、消費者のニーズを満たすプロダクトの提供がますます重要になっています。
この消費者行動の変化を的確に把握し、効果的な価値提案を行うことができれば、市場での競争優位を確立し、持続的なビジネス成長を実現できます。
では消費者の意志決定にはどのような作用が働いているのでしょうか。
「肯定度」が鍵:リピート購入の意思決定
顧客がリピート購入を決める際、最も重要な要素の一つが「肯定度」です。
これは初回購入時だけでなく、購入前から形成される商品やサービスへの好意的な評価が、その後の購買行動に大きな影響を与えます。
では、この肯定度とは具体的に何を指すのかというと、
・商品の品質
・ブランドイメージ
・顧客サービスの質
・価格設定の妥当性
など、複数の要素が組み合わさって形成される総合的な評価といえます。
特筆すべきは、肯定度の形成時期です。
多くの企業が購入後の体験を重視しがちですが、実は情報収集段階での印象が、その後の購買行動を大きく左右します。
そのため、顧客との接点すべてにおいて、一貫したポジティブな体験を提供することが重要です。
さらに、顧客の期待値を超える価値を提供できれば、肯定度は格段に向上します。
この強い信頼関係が築かれると、顧客は競合他社の製品と比較検討することなく、自然とリピート購入を選択する傾向が強まります。
では、具体的にどのような取り組みが効果的になるのか?
例えば、以下ような施策を通じて肯定度を高め、維持していくことが持続的な顧客関係構築の鍵となります。
- 顧客の声を積極的に収集し、製品改善に活かす
- 継続的な双方向コミュニケーションを図る
- 一貫した質の高いサービスを提供する
買い物疲れを避ける心理:リピート購入のメリット
商品やサービスが溢れ、消費者は日々多くの選択を迫られています。
その結果、毎回新しい商品を探し比較検討することが面倒になったり、負担となることがあります。
この「選択疲れ」から解放される方法はあるのでしょうか?
その答えが「リピート購入」です。
すでに満足している商品を継続して購入することで、以下のようなメリットが得られます。
・新製品探しの時間と労力の節約
・品質への不安解消
・購入判断に伴うストレスの軽減
・日常生活の安定感向上
特に効果を実感できるのが、日用品や消耗品のリピート購入です。
毎日使用する商品だからこそ、「使い心地」や「効果」を実感済み。その安心感が、継続購入の大きな動機となります。
そして、このトレンドはビジネスサイドにとっても追い風となります。
つまり、「選択疲れ」から解放されたい消費者のニーズと、継続的な収益を目指す企業の戦略が、完璧な形で合致しているのです。
具体的な施策としては、
・定期購入システムの導入
・ワンクリック再注文機能の実装
・過去の購入履歴からの簡単注文
・会員向け特典の充実
などが効果的です。
このように、リピート購入は消費者と企業の双方にメリットをもたらします。
情報探索と「肯定度」の関係:顧客の行動分析

自ら探し求めた情報:顧客の「肯定度」を高める
お客さんが自分で情報を探す時、それは商品への興味関心の現れです。自分で見つけた情報ほど、信じる気持ちも強くなり、商品への良い印象もアップします。
例えば、欲しい商品についていろいろ調べているうちに、その商品の良さを見つけて「これだ!」となるような感じです。
そのため、企業はSEO対策やコンテンツマーケティングを使い、消費者が自然と情報を見つけられるようにすることが重要です。
消費者は通常、自分の興味や必要性に応じて情報を集める際、企業の公式情報だけでなく、実際に使った人の口コミなども参考にします。
具体的な対策としては、商品の詳しい説明や使い方、実際の使用レビューなどをウェブサイトやブログで分かりやすく紹介することが効果的であり、また、消費者がどんな情報を探しているのかをよく調べて、それに合った内容を提供することも大切です。
このように情報提供を工夫すると、お客様の購入意欲が高まり、繰り返し購入してくれる可能性も上がります。
ただし、提供する情報は正確で役立つものっということが重要です。
専門家のチェックを受けたり、実際のデータに基づいた情報を載せたり、お客様の疑問や不安をすぐに解決できるよう、よくある質問や問い合わせ窓口も用意しておくとベターです。
具体的な検索キーワード:「肯定度」を測る指標
お客様が検索で使う言葉を見ると、その商品への関心度が分かります。特に、具体的な商品名やブランド名で検索している場合は、かなり前向きに検討している可能性が高いです。
逆に、「おすすめの〇〇」といった一般的な検索は、まだ商品についてよく知らない段階です。
一方、「〇〇(具体的な商品名)の使い方」といった検索は、すでに商品に興味を持ち、購入を真剣に考えている可能性が高いことを示しています。
企業は、こうした検索キーワードの傾向を分析することで、効果的な販売戦略を立てることができます。特定の商品名での検索が増えてきたら、その商品のキャンペーンを強化するチャンスかもしれません。
「〇〇の悪い点」といった検索が目立つようなら、商品の改善や顧客サポートの見直しを検討する必要があるかもしれません。
検索キーワードを分析する専用のツールを使えば、どんな言葉で検索されているのか、その数がどう変化しているのかが簡単に分かります。
さらに、広告がどのくらいクリックされているか、ウェブサイトにどのくらいアクセスがあるのかといった情報も合わせて見ることで、より正確にお客様の関心度を測ることができます。
ネガティブ情報も確認:顧客の慎重な行動
冒頭で述べたように、近年のデジタルマーケティング環境において消費者による情報収集行動は、従来以上に徹底したものとなっています。
特筆すべきは、ポジティブ情報だけでなくネガティブ情報も積極的に収集する傾向が顕著になっていることです。
プロモーションや広告担当者、マーケターとして重要なのは、この「ネガティブ情報への関心」を、必ずしもマイナス要因として捉えないことです。
実際、高額商材や長期使用を前提とした製品では、むしろ健全な購買判断プロセスの一部として理解するほうが、戦略を立てる上で有効的です。
また、ネガティブレビューへの対応は、ブランド価値を左右する重要なタッチポイントとなります。
具体的な対応戦略としては、以下の3点が効果的です。
- 問題提起への迅速かつ具体的な回答
- 改善プロセスの可視化
- フォローアップ状況の公開
特に注意すべきは、ネガティブ情報の「隠蔽」や「言い訳」的な対応です。
こうした姿勢は、かえって企業の信頼性を大きく損なう結果となる場合があります。
代わりに、透明性の高い情報開示と具体的な改善施策の提示が、長期的な信頼構築につながります。
実務的なアプローチとしては、例えば以下の施策が有効です。
- カスタマーレビューの全件公開(ネガティブ含む)
- 課題別FAQ・解決事例の体系的な整理
- リアルタイムの問い合わせ対応体制の構築
こうした誠実な対応の積み重ねは、結果として購買意思決定の促進要因となり、さらにはアドボカシーマーケティングへの展開も期待できます。
重要なのは、ネガティブ情報をリスクではなく、むしろブランド価値向上のための重要な機会として捉え直すことです。
これらの取り組みの効果を測るには、ネガティブレビューの割合の変化、問題解決の割合、消費者満足度調査といった定量的な指標と、SNSでの評判分析といった内容で評価する定性的な指標を組み合わせた分析が効果的です。
リピート購入を促すブランド戦略:長期的な関係構築

顧客体験の最適化:継続購入を促す
ロイヤリティを高めるためには、欲しいと思った時に買えるようなシームレスな購買体験の提供が不可欠です。
例えば、Shopifyでも、BASEでも自分たちにとっての使いやすさを重視したECプラットフォームの採用は、顧客離脱を防ぐ効果的な施策となります。
特にスマートフォンでの購入比率が年々上昇する中、マルチデバイス対応は必須です。また、顧客接点の強化という観点から、チャットサポートやFAQの充実も重要な差別化要因となります。
先進企業の事例を見ると、カスタマーサポートの応答時間を数値目標として設定し、KPIとして管理することで、顧客満足度の向上に成功しています。
さらに、定期的なユーザビリティテストやカスタマージャーニー分析を実施することで、継続的な改善サイクルが回しやすくなります。
「Googleビジネスプロフィール」:ローカルSEOの活用
実店舗を持つビジネスは、「Googleビジネスプロフィール」を最適化することで、地域顧客のリピート購入を促進できます。正確な情報を提供し、顧客との接点を増やしましょう。
具体的には、店舗写真のクオリティ向上、営業時間や特別営業日の正確な更新、商品・サービス情報の詳細な記載が重要です。加えて、カスタマーレビューへの積極的な返信(マンパワーに余力があれば)は、ブランドの誠実さを示す絶好の機会となります。
ちなみに、ポジティブ・ネガティブ関わらず、顧客からのレビューに対して返信を自動で行ってくれる便利なサービスも展開してますので、ぜひご一読を。
One Teck Writer
その他、ローカルSEO施策としては、地域性のあるキーワードを意識したコンテンツ制作や、地域メディアとの連携強化が効果的です。また、地域イベントへの参加告知や、店舗独自のキャンペーン情報の発信により、コミュニティとの結びつきを深めることができます。
このような総合的なアプローチが持続的な集客力向上に寄与します。
動画コンテンツの活用:「YouTubeショッピング」連携
テキストや画像よりも多くの情報を伝えられる動画は、顧客の心理に直接働きかけるのに最適なツールです。
例えば、ECサイトへの集客を考えた場合、商品の使い方やレビューを動画で紹介し、そこに購入リンクを貼れば、興味を持った視聴者はすぐに購入できますし、ライブコマースなら、リアルタイムのコミュニケーションで信頼関係を築きながら、購買意欲を高められます。
そして、何より、魅力的な動画は拡散しやすいので、幅広い顧客への認知度アップを狙うことができます。
つまり、新商品やサービスの認知から興味・関心想起→ショップへの誘導(集客)までを動画1つで行えるっという部分が最大のメリットでもあります。
もちろん、単純に動画を作って配信すれば良いという訳ではなく、動画の内容に合わせて適切なキーワードを設定しSEO対策も同時に行うことも重要です。
継続的な関係構築のために:顧客とのコミュニケーション

顧客との対話を重視する:ロイヤリティ向上
顧客とのコミュニケーションは宝の山です。
顧客からの意見や要望を収集し、商品やサービスの改善に活かすことで、顧客のニーズに合ったサービスを提供できます。
また、顧客とのコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことで、リピート購入や口コミによる宣伝効果も期待できます。
例えば、対話重視のためのアクションとしては、以下のような取り組みが有効です。
・問い合わせへの迅速かつ丁寧な対応 (←単純ですがこれが一番大切)
・顧客満足度調査やアンケートの実施 (←定期的な調査は必須)
・ソーシャルメディアやオンラインコミュニティの活用
・顧客サポート部門の強化や顧客管理システムの導入
顧客を飽きさせない:情報とサービスのアップデート
情報・商品・サービスの改善と刷新
常に顧客の生の声に耳を傾け、差別化された体験を届け続けることが、長く支持される秘訣の1つです。
特にオンラインショップでは、人気の高い記事の内容を常に見直し、最新トレンドや顧客の質問に合わせて新しい情報に更新する。また、半年ごとにサイトに新機能を追加し、楽しみを与える等が有効です。
施策例
・人気コンテンツの内容をアップデート (記事の改訂、動画の新バージョン公開など)
・新機能の定期導入 (チャットボット、ARビューアーの実装など)
・季節限定商品の投入 (春夏・秋冬トレンドに合わせた新作投入など)
・リニューアルキャンペーンの実施 (リニューアル記念割引など)
差別化された体験の提供
例えば、植物を専門に扱う店舗やサイトでは、園芸家による詳細な育て方ガイドを商品と一緒に無料で提供。競合にない専門性の高い付加価値で顧客満足度を高めるといった取り組みができます。
施策例
・独自のノウハウ・こだわりを前面に打ち出す (作り手の想いの発信など)
・競合他社にはない特別な付加価値を提供 (専門家による徹底サポートなど)
・ターゲットに合わせた絞り込みで深い体験を (限定モデルの製作など)
購買意欲を高める心理効果:マーケティングへの応用
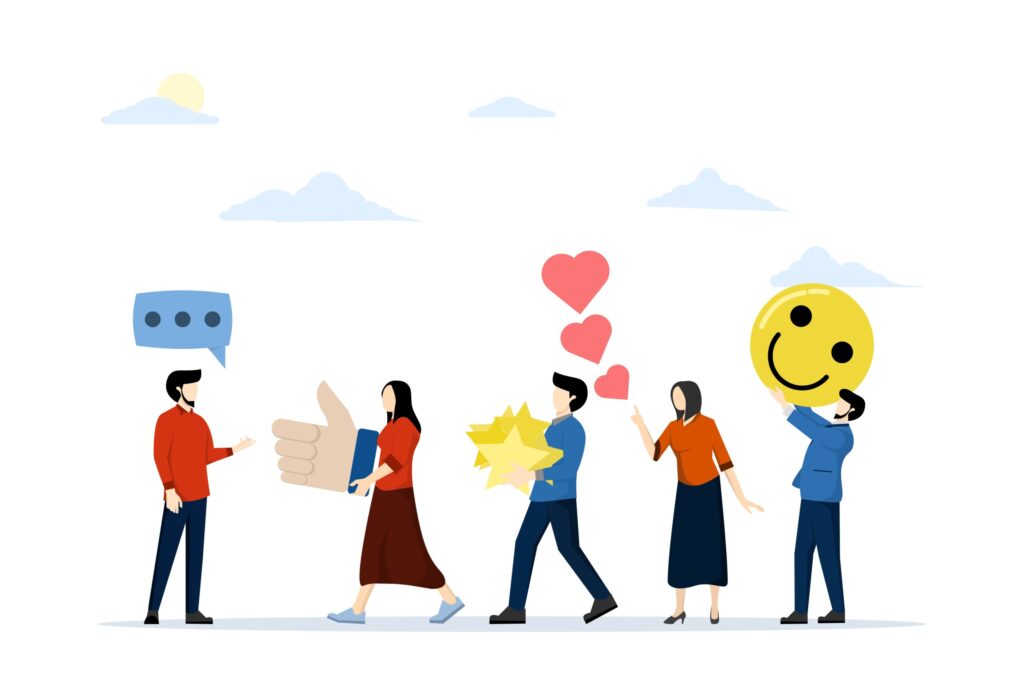
アンカリング効果:価格設定の心理戦略
アンカリング効果は、マーケティング戦略における重要な心理的テクニックです。
初めに提示された価格が「アンカー(錨)」となり、消費者の価格判断の基準として機能します。
非常に単純ですが、アパレルショップで「通常価格19,800円→セール価格9,800円」という表示を目にした時、消費者は9,800円を「お得」と感じやすくなります。
これは最初に提示された19,800円という価格が基準となり、それと比較して判断するためです。
ビジネスでの具体的な活用方法として:
・高価格帯商品と一緒に標準価格帯商品を展示
・セール時の値引き前価格を明確に表示
・プレミアム商品を前面に出し、スタンダード商品への誘導
ただし、この効果を過度に利用すると、消費者の信頼を損なう可能性があります。
重要なのは、商品の本質的な価値を適切に伝えながら、アンカリング効果を補助的に活用することです。
消費者にとって納得感のある価格設定と、透明性のある情報提供を心がけましょう。
単純接触効果:繰り返しの接触で親近感を
「見慣れたものを好ましく感じる」という人間の基本的な心理メカニズム、それが単純接触効果です。
このプリンシプルは、効果的なブランド構築の要となります。
実践的な活用方法として:
・クロスメディアを活用した一貫したブランドメッセージの発信
・SNSでの定期的な情報発信
・店舗やウェブサイトでの継続的な商品露出
・メールマガジンやニュースレターでの定期的なコミュニケーション
などですが、特に注目すべきは質の高いコンテンツを通じた接触です。
単なる露出増加ではなく、以下の要素を意識した情報発信が効果的です。
・顧客にとって価値ある情報の提供
・ブランドストーリーの一貫した発信
・視覚的に印象的なデザインの活用
反面、過度な露出は逆効果となる場合もあります。そのためターゲット層の特性や市場環境を考慮し、適切な頻度でのコミュニケーション設計が重要になります。
社会的証明の原理:他者の行動に安心感を
「人気商品」「売れ筋ランキング」など、普段何気なく目にしている情報はありませんか?
実はこうした情報は消費者の購買意欲を高めるための、重要な心理効果を利用したものです。
それが、「社会的証明の原理」。
人は、商品やサービスの購入を決める際、他者の行動を参考にしたり、周囲の意見に影響を受けたりする心理が働きます。
特に、初めて購入する商品やサービス、高額な商品など購入に迷う場合は、「他の人が選んでいるなら安心」という心理が働きやすくなります。
飲食店であれば、行列ができているお店を選ぶ、ECサイトではレビュー評価の高い商品を購入する、といった行動が、まさに「社会的証明の原理」が働いた結果と言えるでしょう。
ビジネスにおいて、この心理効果を戦略的に活用することは、売上アップに大きく貢献します。
例えば、自社サイトや広告に顧客のレビューや評価を掲載したり、SNSで商品の評判や利用シーンを発信したりすることで、顧客に安心感を与え、購買を後押しすることができます。
ただし、誇張表現や虚偽の情報は逆効果になる可能性もあるため、注意が必要です。
社会的証明の原理を効果的に活用するには、透明性と信頼性を重視し、顧客に「本当に価値のある商品」だと感じてもらうことが重要です。
まとめ:顧客心理を理解し、継続購入を促進
店舗経営やECサイト運営において、顧客のリピート購入を促進するためには、顧客心理の深い理解とそれを基にした戦略的なマーケティングが不可欠です。
その上でまず顧客の「肯定度」を高めるには、商品の品質向上に加えて、ブランドイメージの強化や、密なコミュニケーションが求められます。
特にビジネスにおける差異化を図るためには、競合他社とは異なる独自のブランド体験を提供し、顧客の心をつかむことが大切です。
もちろん、リピーターへの育成には、購入後の体験も重要です。
例えば、素早い配送や親切なカスタマーサポート、アフターサービスをバッチリ提供することが、顧客の「またここで買いたい!」という気持ちを引き出します。
加えて、顧客の購買履歴や行動データを活用し、パーソナライズ。以前の購入内容に合わせた商品提案や、誕生日に特別なクーポンをプレゼントして顧客の購買意欲を盛り上げていきましょう。
そして何よりも、顧客の生の声。
ニーズや要望をキャッチするために、定期的にアンケートや意見募集を行い、そこから得た声をもとにサービスを改善していくことも大切です。
こうして顧客心理を理解し、個々のニーズに応じたアイディアをどんどん試していくことで、リピート購入をどんどん促していけます。
最終的には、顧客との信頼関係を築くことがビジネスの成長には欠かせません。
顧客を大切にして、「ここで買ってよかった」「ここを利用して良かった」と感じてもらえるように細やかな努力を続けることが成功への秘訣です。
さいごに
アイ・クリエイトでは様々なエキスパートがお困りごとについての施策や改善案をご提案させていただきます。
『新規顧客からの問い合わせがない』
『サイト作ったけど放置になっている』
『SNSで発信したいけど、まず何するの?』
『そもそも社内に人材いない』
『サッカーの助っ人がほしい』などなど、
いつでもお気軽にご相談ください。